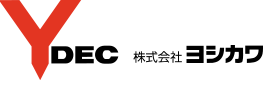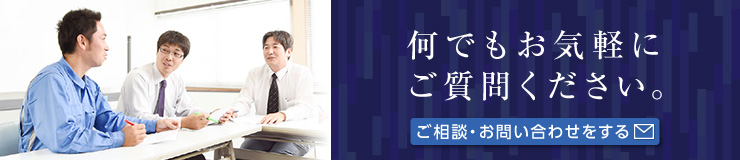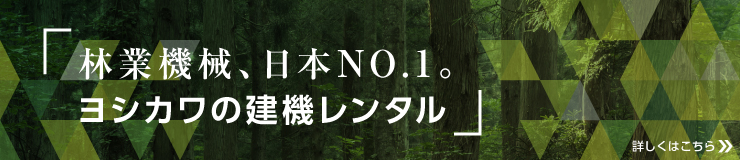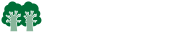
竹林整備の目的・必要性とは
林業 | 2017年8月29日
このテーマへの質問・相談を受け付けております
お気軽にお問い合わせください
春のタケノコは日本の風物詩ですが、その影で日本の森林には危機が迫っています。
人工林をも脅かす「竹林問題」と竹林整備の目的、その必要性についてまとめてみました。
■山を蝕む「竹林問題」とは?
竹はその昔、生活に欠かせない木材の一つでした。
しかし竹材の需要が減り、管理する人のいない「放置竹林」が里山や人工林を脅かす「竹林問題」が深刻化しています。
竹林からの贈り物であるタケノコは竹が伸ばした根っこから生えます。
その長さは3m、長いもので8mほど伸び、山を侵食します。
タケノコも計画的に収穫されるわけではないので、多くのタケノコがそのまま成長し、竹はどんどん増えてゆくのです。
このような竹林問題が全国で発生しており、竹林の整備が急がれています。
■竹林整備の目的と必要性について
竹が増えて竹林が勢力を広げるとどんな問題があるのでしょうか?
竹の根が3mから8mほど伸び、大量のタケノコが毎年竹に成長するというのは説明しました。その先にも問題はあります。
竹が増えると生い茂った葉で日光が遮られ、他の木々の成長を妨げてしまい、やがては竹ばかりになってしまいます。
竹の根は丈夫と言われていますが地表を網のように覆うばかりで、涵養能力はありません。
一方で雑木林や人工林は根を地中深く張るため涵養能力があり、同時に土砂災害などからも山を守ってくれます。
そのため竹によって浸食される雑木を守り、健全な山づくりをするためにも竹林整備は必要なのです。
■竹林整備にあると便利な機械や整備を行うのに適した時期について
竹林整備は手作業で行う場合もありますが、竹を切断する専用の機械なども導入されています。
竹は通常の木と違い、切断した後に斜面から滑り落ちる事が多く、作業者にとってリスクがあります。
竹林整備用の機械はそのようなリスクを減らすため、伐採した後も垂直のまま運搬できる仕様となっています。
伐り取った後の竹はそのまま竹用の粉砕機にかけられてチップ材として利用されます。
また竹を伐る時期は他の森林と同じように竹に水が上がらなくなる11月前後が適していると言われていますが、荒廃した竹林を除去する作業の場合は特に時期はなく、作業のしやすい日が選ばれています。
このテーマへの質問・相談を受け付けております
お気軽にお問い合わせください